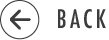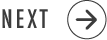- 2025/11/13
人も自然も豊かに生きる「津和野町の理想の未来」を考えるワークショップを実施しました




- 牛木 力



10月4日(土)~5日(日)に、自分らしさを大切にしながら社会全体が豊かになる「未来の津和野町」のあり方を考えるワークショップを、一般社団法人津和野まちとぶんか創造センター(TMC) さんと共催し、当財団のみらい共創コーディネーターがこの2日間のファシリテーターを務めました。
2日間のワークショップには、町内の高校生や大学生、町の若者など約20名が参加しました。
テーマは「Conviviality(コンヴィヴィアリティ)=ともに生きる」
Conviviality(コンヴィヴィアリティ)という言葉は、思想家イヴァン・イリイチ(Ivan Illich) が1970年代に提唱した概念で、“人が人らしく、他者や自然と共に生きる力”を意味します。彼は『コンヴィヴィアリティのための道具(Tools for Conviviality)』の中で、「人が他者や自然と共に生きるための道具や関係のあり方」を問い直しています。つまり、convivialityとは“ともに生きるための自立的な関係性”です。
今回のワークショップは、この考え方を、楽しみながら体感していく時間でした。
トットネスという町、シューマッハ・カレッジという学びの場
講師には、イギリス南西部デヴォン州の小さな町トットネスにある大学院大学「シューマッハ・カレッジ(Schumacher College)」から、エマ・キッド(Emma Kidd)さんとジェイ・トンプト(Jay Tompt)さんを招きました。
トットネスは、世界で初めて「トランジション・タウン(Transition Town)」運動が始まった場所として知られています。化石燃料への依存や気候変動の問題を前に、「地域の力で持続可能な暮らしをつくる」という試みがこの町から世界へ広がりました。エネルギー、食、経済、教育などを地域の中で循環させようとする活動がいまも息づいています。
その中で生まれたのが「Community of Dragons(コミュニティ・オブ・ドラゴンズ)」というユニークな仕組みです。
これは、地域の起業家や若者が自分のプロジェクトを発表し、市民が応援するというものです。ここで交わされるのは、お金だけではありません。人々は自分の「Offer(オファー)」、つまり時間、知識、場所、つながり、技術など、自分にできることを差し出し合います。中には、応援のハグや、子どもを預かる券といったオファーもあります。
1日目:五感でまちを感じる——津和野を歩き、聴く
初日は、エマさんによるワーク「津和野を五感で感じるまち歩き」を行いました。
参加者は、石畳を歩く音、瓦屋根が織りなすパターン、木の香り、風の流れ、川のせせらぎなど、ふだんは意識しない感覚に耳を澄ませました。



「もし津和野が人だったら、どんな性格の人だろう?」
そんな問いが投げかけられ、参加者はそれぞれ感じたイメージを言葉にしました。
「優しい風のよう」「母のように包み込む存在」「円のような閉じた形」
津和野という町を「生きている存在」として感じ取る体験でした。
このまち歩きの思想的背景にあるのが、エマさんの専門でもあるゲーテ的観察法です。
ドイツの詩人・思想家ゲーテは、自然を「外から分析する」のではなく、「関係の中で感じる」ことを重視しました。観察者は対象と一体になり、感覚と想像力を使って現象の“生命”を理解していきます。エマさんはこの方法をまちの観察に応用し、「津和野の生命を感じ取る」体験を導いてくれました。



2日目:ともに描く未来——Convivialな社会とは
2日目は、ジェイ・トンプトさんによるワークショップを行いました。
参加者は、自分が暮らしたい未来の津和野町を、目を閉じてイメージし、その後、スケッチや言葉で描き、それを実現するためにどんな仕組みや取り組みがあればよいかを語り合いました。






「経済」「教育」「自然」「文化」など、さまざまな視点が交差する中で、「経済の仕組みを考えることが、幸せを考えることとつながる」という気づきが生まれていました。
参加者からは、
「未来の町の理想の姿を、経済面も含めて考えるきっかけになった」
「町のこれからを自分ごととして考えたい」
等の声があがり、会場には笑顔と真剣さが交錯する温かい空気が広がっていました。



津和野町から始まる“ともに生きる”未来
今回のワークショップで育まれたのは、「津和野町をどう活性化させるか?」という外向きの問いではなく、「私たちはこの町と、どんな関係を結びたいか?」という内なる問いでした。
町を“感じる”ことから始まる学びは、町を“つくる”ことの最初の一歩です。
シューマッハ・カレッジやトットネスで培われた思想が、津和野という町の土壌と出会った2日間となりました。
「感じる」「語る」「差し出す」という小さな行為の積み重ねが、町と人がともに生きる未来の礎になっていきます。
津和野町で過ごしたこの時間は、小さな町から始まる「Convivial(ともに生きる)」実践の記録であり、これからの教育や地域づくりに向けた、静かな、けれど確かなヒントになりました。



自身が住みたいと思う町について主体的に考え、それを実現するにはどうすれば良いのかを共に考える機会をこれからも創出していきます。
※写真:一般社団法人津和野まちとぶんか創造センター提供